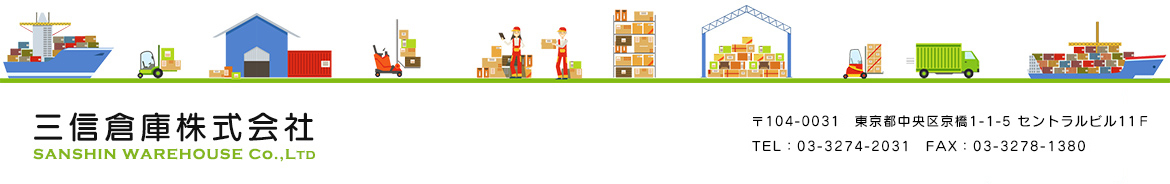50年誌

おかげさまで三信倉庫は2005年2月に創立50周年を迎えることができました。
これを機にささやかな記念誌を作成いたしました。
会社の歴史を読みやすく編集したつもりです。
私たち50年の足跡を礎に、お取引様に愛される会社を目指しさらなる努力を結集する決意をしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
Ⅰプロローグ
三信倉庫本社応接室に一体の胸像と一枚の写真がある。どちらもこの会社の創業者大竹仙松を写しとったものだ。胸像は仙松51才、写真は76才のとき。25年の歳月は当然のことながら風貌を変化させたが、鋭い眼光は変わらない。
三信倉庫の歴史を語るとき、やはり事業欲旺盛なこの創業者に言及しなければならない。
明治32年(1899年)愛知県吉良吉田に生を受けた仙松は豊橋商業高等学校を卒業後、総合商社兼松の前身兼松商店に入社し、海外雄飛の夢を温めた。この夢は自身の肺結核発病のため断念せざるを得なかったが、病気治癒後、神奈川県川崎市で材木商を営んでいた兄を頼り上京したのが起業家としてスタートするきっかけとなった。
仙松は兄の仕事を手伝いながら事業資金を蓄え独立した。アパート経営、タクシー会社など順調に業績を伸ばしたが我国は太平洋戦争に突入、一時軍需産業にも手を広げたことがあった。戦後の復興期にいち早く不動産の将来性に着目、その後の三信倉庫本社の敷地となる東京駅前のセントラルビル用地を取得した。
一方、戦時中軍部の要請で芝浦の都有地に木造平屋建て17棟の倉庫を建設。陸軍の軍需物資保管のため賃貸することになった。
これが後の三信倉庫発祥の礎となるのである。
戦後の混乱期がようやく収まり人心に将来への希望がともされるようになった頃、セントラルビルの建設に着手。昭和26年(1951年)竣工した。
セントラルビルに事務所を構え、建設会社、ビル賃貸管理会社、宅地造成分譲会社、無尽会社、人造宝石会社、損害保険代理会社、マンション管理会社、ゴルフ場会社などを次々に設立、そのなかの一つが営業倉庫業の三信倉庫であった。これらの会社は事業として成り立たなかったもの、一定の成果をあげたのち清算したもの、現在まで存続しているものなどさまざまであるが、三信倉庫はこれらグループ会社の中核として育っていった。
仙松はただ事業のみを追い求める人物ではなかった。地球上から戦争を絶滅するという大志を抱き、昭和47年(1979年)には財団法人大竹財団を設立し、著書「平和へのライセンス」を上梓したり、市民運動を後援するロマンの人でもあった。
胸像の制作年はセントラルビルの竣工年にあたる。三信倉庫の設立はそれより4年のちとなるのだから、仙松の55才。旺盛な事業意欲から生まれた会社群としてはやや遅い旅立ちと言えよう。
Ⅱ創成期
陸軍の軍需物資を保管していた芝浦の倉庫は終戦と同時にアメリカ軍に接収され、今度は進駐軍の物資を保管することとなった。東京湾から本土襲撃を仕掛けた米軍の戦闘機は、進駐後に使えそうな倉庫を爆撃の対象から外したとのうわさもある。
サンフランシスコ講和条約も締結され、芝浦倉庫は昭和30年(1955年)晴れて接収解除となり、三信倉庫の一歩は始まった。

芝浦営業所の倉庫群(昭和45年頃)
設立後の諸施策は矢継ぎ早だった。
昭和31年(1956年)5月西芝浦倉庫を買収。 同月、浦和倉庫を買収。同時に浦和営業所を開設。
同年9月芝浦営業所開設。
さらに翌年の昭和32年(1957年)3月には品川倉庫新築。この間、昭和31年(1956年)に、農林省植物防疫所、農林省指定倉庫の指定、保税倉庫、倉庫証券発行などの各認可を取得。急速に営業倉庫としての基盤を整えた。
昭和37年(1962年)の倉庫業法の改正に伴い新業法の下での営業許可を取得した。
翌年2月には品川倉庫のA棟(現旧館)を新築し、品川営業所を新設した。

西芝浦倉庫(昭和45年頃)

芝浦営業所公園倉庫(昭和45年頃)

浦和営業所(昭和45年頃)
昭和41年(1966年)10月にはサンウェーブ工業様の要請で仙台営業所を開設して、現在の4営業所体制の基礎が出来上がった。サンウェーブ工業様は当時全国の物流網を完備すべく、そのパートナーとして三信倉庫を選び、その第一陣として仙台に倉庫を設けたが、その後サンウェーブ工業様の方針転換で物流子会社サンウェーブ運輸倉庫様を設立、三信倉庫の全国展開は夢に終わった。

品川営業所(昭和38年頃)

仙台営業所(昭和45年頃)

現在の仙台営業所
この頃の倉庫業の例に漏れず主な荷主は農林省で、政府米の保管に相当な面積を費やした。また他社に先駆けて家庭電化製品の保管に乗り出し、この頃東京進出を図りつつあった松下電器産業東京営業所様の電気製品を大量にお取り扱いさせていただいた。ただしじきに松下電器産業様の物量の増大は三信倉庫一社での保管管理能力を越え、同業他社の協力を得ながら主に首都圏の販売会社関係の物流管理にあたった。
創成期の事業展開はこのように短期間で急速に行ったため、倉庫の賃借や、建物は取得しても底地は借地が多く、経営基盤の確立のためにも徐々に底地を取得していく必要があった。その皮切りとして、昭和46年(1971年)西芝浦倉庫の底地を取得した。この3年後には老朽化した倉庫建物を取り壊し鉄骨鉄筋造り5階建倉庫を新築、この後も各営業所の建物を災害に強い建物に建て替えていくことになる。

現在の西芝浦倉庫
Ⅲ成長期
昭和50年(1975年)に後継社長として就任した大竹広明は、台風や地震、火災に弱い建物から災害に強い建物への変身を画策、ひいてはそれが荷主の信頼を増すために重要と考え一連の建物改築計画(チャレンジ計画)を始動した。
同時に建物を新築するにあたり、倉庫にはこだわらずその立地を最大限に生かす用途にして、最大の付加価値を得ることを基本とした。
また平屋建て倉庫を多階建てにすると面積が増える。寄託営業と賃貸営業とのバランスをどのようにとっていくかという課題に、現有社員数で管理できる面積は寄託営業を継続し、増えたスペースについては安定収入を得るために賃貸する方針を明確にした。
浦和ビル
浦和営業所は、旧ミシン工場の建物を買収したもの。一部はそのまま倉庫に利用し、一部は倉庫に建て替え営業してきたが、昭和52年(1977年)地主から借地権と底地の等価交換方式による所有権取得を提案された。約3割の土地を地主に返還するのと引きかえに、残りの7割の土地の所有権を取得する提案に乗り、この土地における建物新築が可能になった。営業所開設当時は周囲に畑が多かったこの界隈も、この頃には住宅が増え、倉庫に出入りするトラックが周辺住民の迷惑になるとの苦情も寄せられ、倉庫移転の決断を迫られていた。
わが国も急速な経済成長で首都圏の人口が急増、加えてモータリゼイションの伸張で、郊外型大型店舗の需要が高まっていた。浦和営業所はこのような大型スーパーの立地にふさわしく、5社ほどの全国展開チェーンから出店の申し込みがあった。会社では各社の条件を慎重に審査、加えて取引先銀行や、取引先荷主から強く押された長崎屋様を選定、手を組んで出店に向けて歩み出した。大型店の新規出店には二つの大きなハードルがある。ひとつは近隣商店街や地元商工会議所のOKをもらうこと。 もうひとつは近隣住民の同意をもらうことである。長崎屋浦和店の出店に際してはこの両方ともが大きな障害となった。特に近隣住民の反対は共産党をも巻き込んだ大きな運動となり、結局地上4階建ての計画のところ一層ずつ下げて、地下1階地上3階建ての店舗として昭和59年(1984年)7月に竣工、同9月に開店した。

浦和の商業ビル
なお店舗の建設にあたり昭和58年(1983年)7月板橋営業所を開設、浦和の荷主貨物を移転した。

板橋営業所
品川倉庫
昭和40年(1965年)当時、三信倉庫には多階建ての倉庫は品川営業所に1棟あるのみだった。その後各営業所で堅牢な建物に建て替えていったが品川の敷地内には2棟の平屋建て木造倉庫が残っていた。東京はビジネスゾーンが拡大し従来は倉庫街だった日本橋や芝浦にオフィスビルが進出、倉庫は港湾近くの埋立地に移転していた。三信倉庫ではこのような状況下、品川営業所の位置する天王洲は東京南部の物流最前線として機能するとの判断から、3階建ての旧倉庫に隣接して6階建て倉庫を建設することになった。この新棟は竣工直後から三井倉庫様、富士物流様そして寺田倉庫様といういずれも同業の会社にお貸しして現在に至っている。しかしこの地区が東京の物流最前線との読みは見事にはずれ、天王洲の再開発で島内は高層オフィスビルが林立し、将来、倉庫取り壊しの時には他用途への転換を余儀なくされている。

品川営業所
公園ビル
芝浦は倉庫の街であるとともにオンワード樫山様の一大拠点でもある。オンワード樫山様から、隣接した三信倉庫芝浦営業所の土地建物を譲ってもらいたいとの交渉を何度か受けていた。しかし三信倉庫は当該土地の底地を取得していなかったため、近接の公園倉庫の取り壊しと、オンワード様仕様の建物の建設、賃貸を提案、これが受け入れられて昭和61年(1986年)7月、地上7階建ての物流ビルが完成した。
建物は商品の流通管理を目的としているものの、事務量の増大に対処して、オフィススペースに転換できるような構造になっている。その目論見どおり、現在では4階から7階は事務所としてお使いいただいている。 取り壊した旧倉庫は埠頭公園の隣にあったので公園倉庫と名づけていた。新しいビルにも公園の名を残し、社内では公園ビルと呼称している。

公園ビル
ループ
芝浦営業所は三信倉庫営業の発祥地でもあるが、土地が東京都からの借り物で、しかも1年毎の短期借地契約のため、恒久的建物が建てられないという悩みがあった。三信倉庫は早くから底地の払い下げを画策してきたが、敷地内に旧陸軍の鉄道敷設計画があり、このため東京都も独自に払い下げを決定することができなかった。旧陸軍の路線計画を受け継いだ国鉄(現在のJR)がせっかくの権利を留保していたためである。会社は昭和40年(1965年)ごろから毎年のように払い下げの陳情を行ってきたが一向にらちが開かない。結局昭和60年(1985年)に永年の努力が実り払い下げが決定、ようやく独自に建物を建設できるところまで漕ぎつけた。しかしこの頃は既に土地価格が高騰し、普通の倉庫では土地代まで回収するのは不可能な状況になっていた。そこで付加価値の高いオフィスビルの建築を決断したのである。
総事業に占める土地代金の比率を少しでも薄めるため容積率限度一杯の建設計画を立てた。さらに港区では都心の定住人口増加政策のため、一定規模以上の開発には敷地と同面積の住居の付置義務条例を施行、芝浦でもオフィスの他に住居の併設を求められた。
今回のプロジェクトは今までの建設とは規模が大きく異なるため、計画段階から賃借予約していただけるテナントとの契約を先行し、取引銀行からご紹介のあったリクルート様と手を結ぶことになった。敷地が鉤型で海に面していることから、眺望を生かしたオフィス棟とマンション棟の2棟を建設し、事務所と住宅という相反する使用勝手機能を分離することとした。設計は順調にすすみ、総合住宅設計制度による容積率の割り増し、さらに優良建築物に対する港区の補助金制度にも合致することがわかり、早速申請した。ところがこのときあのリクルート事件が発覚、政界、財界を巻き込んだ大事件となった。もちろん三信倉庫はこの事件には無関係で正々堂々としたものであったが、一部の新聞にあらぬ疑惑を書き立てられ、港区も万一世論の反発を買うのは得策でないとの判断から、三信倉庫に補助金申請の取り下げを行うよう要請があった。会社はやましいところがないのでそのまま放っておいたら、いつの間にか申請人(三信倉庫)自らが取り下げた形になっていた。またこの間、総合住宅設計制度が緩和され、さらに6階分ほどマンションが建て増しできる見通しが立ったので、建築時期を1年間ほど遅らせて地上18階建てのマンションが完成した。

左側ループX 右側ループM
17階建てのオフィス棟は基準階300坪の無柱空間を実現し、インテリジェントビルとして高機能を誇っている。たまたま建設計画中にレインボーブリッジが着工、完成した美しい吊橋はオフィスやマンションから見た東京港、お台場の景色に花を添えている。
自然界のなかでもっとも完成された円。さらにいつまでも上昇していくイメージでこの地域開発をループと命名。レインボーブリッジ・ループ部分が目の前にあるため覚えやすく、皆様に親しまれている。「あらゆるものを創造する可能性を秘めたスペース」との意味を込めて、事務所棟をループX、マンションの頭文字をとって住宅棟をループMと名づけた。 なお取り壊した倉庫に保管していた貨物は品川営業所に移管したが、すべて収容しきれなかったので、品川埠頭内の新幹線高架線下の倉庫を賃借して、品川埠頭出張所とし現在に至っている。

品川埠頭出張所
戸塚倉庫
ループの建設で、災害に弱い建物を耐久耐火性の強い建物に改築するチャレンジ計画は完了した。次にサテライト計画と銘打ち東京近郊に衛星(サテライト)状に物流拠点を配置していく計画を立案、その第一弾として横浜市戸塚区に売り物件として情報の入った倉庫を取得。現在でも当初からのお客様スリーエスサンキュウ様にお使いいただいている。建物は地上3階建て。今までの三信倉庫に多く採用されていた低床式とは異なり、長さ40メートルの高床式プラットフォームを設備、流通型倉庫の機能を発揮している。
これまでは倉庫は中身が肝心とばかり、外壁への社名の掲示は積極的に行ってこなかったが、板橋、品川に続いて戸塚にも三信倉庫の社名を表示、東海道線、横須賀線から良く見える建物と社名は、会社名の浸透に大いに役立っている。
サテライト計画についてはその後格好な物件がなく、積極的な展開はしていない。

戸塚倉庫
東京花き共同荷受㈱
大手建設会社から、生花の仕分け作業会社の移転情報が飛び込んだ。練馬に所在する東京花き共同荷受株式会社が東京都から立ち退き勧告を受けている。その代替地は大田区城南島だが、練馬と城南島では土地単価が倍も違い、移転しても土地の半分は使い切れないのでパートナーとなる物流会社を探しているというもの。今後の首都圏の物流を見据えたとき、羽田空港の北側に位置する城南島は是非進出したい地域。早速先方の担当役員と面談、提携に向けて漕ぎ出した。
当方の思惑、先方の条件をつき合せていくうちに、双方の利益が一致するのは三信倉庫が東京花き共同荷受をM&Aすることとの結論に行き着いた。紆余曲折はあったものの平成7年(1995年)10月、無事株式譲渡契約書を取り交わし、三信倉庫のグループ入りをすることとなった。
花の仕分け配送は主に夜の8時から朝の5時頃までの業務。倉庫の始業時には花の仕分け場は段ボール箱ひとつない広い荷捌き場となり、昼夜二業務を行えるところから倉庫の二毛作と命名、資産の有効活用に貢献している。
1階は共用荷捌き場、1階の一部と2~4階は富士物流様、5階は三信倉庫城南島流通センターがそれぞれ保管庫として利用している。また品川営業所にあった三信運輸もトラックの増加に伴い拠点を城南島に移転、営業展開の幅を広げた。
三信倉庫と東京花き共同荷受は組織上別会社であるが、事務所やコンピューターシステム、営業の共同化を推進し、相乗効果を高めている。
外壁には緑と赤の巨大なリボンを描き、お客様の大切な商品を心を込めて丁寧に扱わさせていただく姿勢を表現した。
また建物の上空は羽田空港へ離発着する航空機の航路となっているため、屋上に"Good Luck 三信倉庫"と大きく描き、運行の安全を祈るとともに、乗員や乗客に対し社名をアピールしている。

城南島流通センター
Ⅳさまざまな取り組み
三信運輸㈱
それまで協力会社として運送をお願いしてきた有限会社浜田産業が昭和55年(1980年)組織を強化し、三信運輸株式会社として再発足、5年後に三信倉庫は自動車運送取扱事業の登録をして、名実ともに足を持った倉庫として、お取引先の円滑な物流に対応できる体制を作った。
三信運輸は現在も城南島流通センター内に拠点を構え、三信倉庫の重要なパートナーとして、強力な提携関係を保っている。
Booksあすよむ
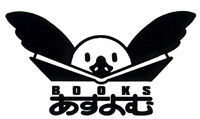
書籍は(出版社→取次店→書店)のルートで流通する。このシステムは大手出版社には都合がよいが、中小零細出版社には最善の機能を果たしているとは言いがたい。なぜなら大手出版社は売れる見込みのある本は優先的に全国の書店に配本され、書店の見やすい棚に置かれるシステムだからである。社会的に有益な本、小数部でも優良な本を読者に提供したいとも思いを実現するため、社会科学系の出版社数社と三信倉庫が手を組み、”Booksあすよむ”を立ち上げた。
読者からのご注文のを板橋営業所内の”あすよむセンター”で受付け、倉庫に常備している本のをペリカン便に乗せ明日にはお届けするというサービス。当時はブックサービスもアマゾンドットコムもなく、画期的な流通として話題を集め、テレビニュースなどにも何回も取り上げられたが、結局は配送料金と代引き手数料がネックになり、後続宅配会社の参入で大きな伸びは示せなかった。しかしこのビジネスを契約に書籍の改装業務を受注し、倉庫内での流通加工の幅を拡大した。
ときめき21
会社の中長期経営計画の策定にあたって委員会を発足、5年後の計画到達年が21世紀にあたることから、この計画を“ときめき21”と名づけた。委員間の熱い議論を経て、平成8年(1996年)に計画を発表した。
委員会ではまず現状の分析を行い、同業他社の経営数値分析、お取引先や従業員の意見聴取などをもとに12項目の目標を盛り込んだ。
計画は作りっぱなしの弊害を避けるため、一年毎に各項目の達成度を部門別に発表、売上高などデフレ要因による未達成項目はあったものの、社内活性化の所期の目的は達成できた。
なお“ときめき21”で制定した経営理念「私達は人と物と環境を大切にして、社会にとってかけがえのない役割を果たします」は今も社員の共通目標として、会社の進むべき道を明示している。
ハニカムシステム
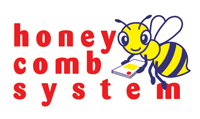
パソコンの普及とともに、ウェブ上での商品発注が増加している時代の流れを読み、インターネットで受注した商品の仕分け、発送業務を一括して受けるシステムを構築。“ハニカムシステム”と名づけた。ミツバチが花粉を集めて巣の中で蜂蜜に仕上げることに習い、倉庫内の流通加工により、商品の付加価値を高めることからこの名前にした。
ゆとりくん

三信倉庫は企業物流の受託が多く、いわゆるBtoCの分野には進出していなかったが住宅地をそばに控える営業所で、トランクルーム業務を開始。書類、家財、タイヤなど普段は使わない家庭や事務所の雑品をお預かりしている。“ゆとりくん”とは、倉庫業者にアウトソーシングすることにより、家やオフィスにゆとりができるような思いを込めている。
このシステムは若手社員で構成したフラッシュボイス(後述)が企画、立案、実行したものである。
アクアクララ
倉庫スペースを使った新しいビジネス。これは三信倉庫が継続して希求しているテーマである。
アクアクララジャパン様からのご提案は、まさにこのテーマに合致したものだった。
地球環境の悪化に伴い、食料や飲料に対する健康志向は年を追って増している。こんな社会環境を見据え、ベンチャー企業アクアクララジャパン様が西日本の拠点展開をほぼ終えて東日本の拠点整備に注力した頃、三信倉庫にもお誘いがあった。新規の事業には計画立案から実行までかなりの時間が必要なものだが、この件に関しては三信倉庫の対応は素早かった。お誘いの話をお受けしてから5ヵ月後にはプラントが完成し、試作品がラインから生産された。
現在ミネラルウォーターの12リットル入りガロンボトルラインと、ウーロン茶など各種機能水を製造するペットボトルラインの2本のラインが稼動し、アクアクララジャパン様の認定資格を取得した三信倉庫社員が製造にあたっている。
同業者からは、倉庫内でミネラルウォーターの生産と驚かれるが、倉庫内で水道水をろ過しミネラルウォーターや機能水を生産することは、究極の流通加工と自負している。
スプラッシュ
創業時「伊豆美」という社内報が発行されたことがあったが、いつの間にか廃刊になった。「伊豆美」は社内の情報誌というよりも論文集、作文集の色彩が強かった。
平成9年(1997年)、社内の風通しを良くするために社内報の発行を決定、ほとばしる活力を表す“SPLASH”と名づけられた。たった60部ほどの発行部数なので印刷会社に頼むと割高になる。そこで編集、割付、印刷、製本まですべて社内で作成することにした。高性能になったパソコンやカラープリンターの恩恵に浴したのは言うまでもない。
東京商工会議所主催の社内報コンクールに何度も応募したが、手作りの可愛い社内報との評価はいただけるものの、大手企業の社内報を凌駕するにはいたっていない。
フラッシュボイス
新規事業、多角化を模索するために若手社員からなるプロジェクトチームを立ち上げ、既存の組織を通さず社長直結の部署横断的な委員会として機能、自由で型破りな提案が続出した。“ゆとりくん”はその中から生まれた産物。
現在その精神は“新創”(後述)に受け継がれ、これからの三信倉庫が進むべき道を若手社員が熱心に討議している。
ISO9001認証取得

倉庫作業の品質管理、これは創業以来先輩から後輩へ、会社の重要なノウハウとして受け継がれてきた。
しかし作業の標準化、社員の意識向上にはISO9000シリーズの認証が必須と考え、認証取得に取り組み、平成14年(2002年)6月、晴れて全営業所倉庫業務を対象にISO9001・2000年版が認証された。
記録の保存、内部監査、情報の伝達、外部審査を通して、社員の意識向上、情報の共有、作業手順の改善、そして顧客の信用拡大に役立っている。
社内独自の品質管理は、ともすると井の中の蛙に陥る危険もあるが、ISO9001の認証取得によってより高度な品質管理に向けて、あくなき前進を続ける下地ができた。
Ⅴスプリングボード
企業の寿命は30年といわれることがある。企業が変革しないと社会の変化に取り残されて滅びてしまうということであろう。それを避けるには企業は常に自己改革をしていなければ生きぬけないことになる。三信倉庫はその30年をとうの昔に過ぎた。果たしてこの50年、社会の変化に対応した変革が遂げられてきたのであろうか。会社はこれが完成ということはない。常に悩み、迷いながら将来のために日々努力している。
創業50年という節目には、通常立派な50年史を発刊し、お取引先にお配りするものだが、三信倉庫は過去を振り返るよりも将来を見据えることに重点を置くべきと考えた。そのひとつが、将来の会社のあるべき姿を議論するプロジェクトチーム「新創」の立ち上げである。社員全員にインタビューしてさまざまな意見を汲み取り、次の時代に生かせる方策を実現していくことになる。
もちろん「温故知新」、これまで営々と会社を築いてこられた先輩方の足跡を糧にして将来を見据えることも大切であり、そのためにこの小冊子を作成した。先輩方が汗水たらして築き上げられた会社を育てていくために、現社員はよくその歴史を理解してほしい。
今、資産を持つためのリスクが喧伝され、バランスシートから資産を除外する経営がはやっているが、現時点で三信倉庫はその潮流には乗らない。それよりも、せっかく保有している資産を有効に生かす経営が大事であると見定めている。資産を持たないよりは持っているほうが有利であることは自明だし、その強みを生かしていくのが私たちの経営だ。
会社にとって50年とは単なる節目に過ぎない。私たちはこの節目にあたり、過去の貴重な礎の上に新たな飛躍を期している。まさにスプリングボードにのって跳躍をするがごとく。
企業は永続するものだが、それを構成する人は入れ替わる。これからの50年、そしてその先に三信倉庫がどのような変革を遂げているかを想像するのは大いに楽しみだ。
100年史、何人の人が読めるだろうか。

東京駅前のセントラルビル
Ⅵ年表
| 昭和30年(1955) 2月 | 設立登記 資本金500万円 | ||
| 11月 | 倉庫営業開始 | ||
| 31年(1956) 4月 | 資本金2000万円に増資 | ||
| 5月 | 西芝浦倉庫を買収 | ||
| 5月 | 浦和倉庫を買収 営業所開設 | ||
| 5月 | 農林省植物防疫所に指定される | ||
| 6月 | 農林省指定倉庫に指定される | ||
| 7月 | 保税倉庫許可 | ||
| 9月 | 芝浦営業所開設 | ||
| 11月 | 倉庫証券発行許可される | ||
| 32年(1957) 3月 | 品川倉庫新築 | ||
| 35年(1960) 6月 | 浦和倉庫新築 | ||
| 36年(1961) 4月 | 資本金3000万円に増資 | ||
| 37年(1962) 5月 | 倉庫業法改定に基づき営業許可される | ||
| 38年(1963) 2月 | 品川倉庫新築(A棟) 営業所開設 | ||
| 5月 | 浦和倉庫新築(9号) | ||
| 39年(1964) 6月 | 資本金6000万円に増資 | ||
| 41年(1966)10月 | 仙台営業所開設 | ||
| 42年(1967) 8月 | 浦和倉庫新築(4,5号) | ||
| 43年(1968) 5月 | 仙台倉庫新築(本棟) | ||
| 46年(1971) 4月 | 芝浦土地買収(第一次) | ||
| 4月 | 品川土地買収 | ||
| 12月 | 西芝浦土地買収 | ||
| 49年(1974)10月 | 西芝浦倉庫新築 | ||
| 52年(1977) 3月 | 品川第一事務所新築 | ||
| 5月 | 仙台倉庫新築(新棟) | ||
| 12月 | 浦和土地所有権取得 | ||
| 55年(1980) 5月 | 浦和土地買収(第二次 | ||
| 7月 | 三信運輸㈱設立 | ||
| 56年(1981) 5月 | 品川第二事務所新築 | ||
| 57年(1982) 5月 | 三信運輸㈱運送免許取得 | ||
| 11月 | 品川倉庫新築 | ||
| 59年(1984) 9月 | 浦和ビル新築 | ||
| 60年(1985) 4月 | 芝浦土地買収(第三次) | ||
| 8月 | 自動車運送取扱事業登録 | ||
| 61年(1986) 7月 | 芝浦公園ビル新築 | ||
| 62年(1987) 3月 | 芝浦土地買収(第四次) | ||
| 63年(1988) 2月 | Booksあすよむ営業開始 | ||
| 平成 元年(1989)10月 | 品川埠頭出張所開設 | ||
| 3年(1991)11月 | 芝浦にLoop-X,Loop-M新築 | ||
| 4年(1992) 4月 | 戸塚倉庫買収 | ||
| 6月 | 資本金1億2000万円に増資 | ||
| 7年(1995)10月 | 東京花き共同荷受㈱に経営参画 | ||
| 9年(1997) 3月 | 城南島流通センター新築 営業所開設 | ||
| 12月 | 社内報SPLASH創刊 | ||
| 11年(1999) 5月 | 城南島流通センターに定温倉庫設置 | ||
| 12年(2000) 6月 | ハニカムシステム稼働 | ||
| 14年(2002) 6月 | ISO9001・2000年版の認証取得 | ||
| 7月 | 私募債(第一回)発行 | ||
| 9月 | ゆとりくん営業開始 | ||
| 15年(2003) 9月 | 私募債(第二回)発行 | ||
| 16年(2004) 1月 | アクアクララプラント生産開始 | ||
| 7月 | 私募債(第三回)発行 |